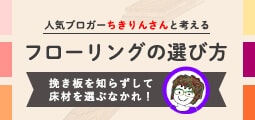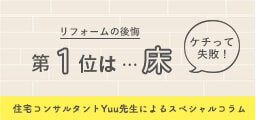「図」と「地」のせめぎあいの中に
空間の印象が浮かび上がってくる

「図」と「地」とは何か―。
インテリアデザインにおいては壁や床、天井などが「地」であり、家具や装飾などが「図」であると考えます。少し専門的な表現をするならば、「図」とはインテリア空間の中で意匠的なエレメント(構成要素)のことであり、「地」とは、インテリア空間全体のベースということになります。
例えば、白い壁に囲まれた部屋に樹木のようなオブジェのエレメントが一本入っただけで空間の印象は変貌します。その変化は劇的ともいえるものです。また、「図」となるエレメントは決して、もとから装飾的につくられたものだけとは限りません。
テーブルカウンターや棚であっても「図」として、空間の印象をつくり出すことができるのです。棚などは空間の中で、普通なら印象から消えてしまう存在ですが、あえて空間の象徴的存在としてデザインすることもできるのです。
僕の作品の一つで、安藤忠雄さんの設計した神戸のデザインズゲートの中にあるメンズブティック「ヨウジヤマモト」も、その一例です。唯一、中央に配置された、単純な形態の棚だけが何もない空間の中心を形成しています。実は、この作品が「日本的空間原理の本質」を内包していることに、やがて気づきました。

ヨウジヤマモト…空間の単純化を試みていた1980年頃から、何もない空間の密度や、静けさのもつ強さに気づきはじめた。それは日本文化の特性とも重なり合うものであった。素材感や形態、装置などから表層と空間的属性を排除した実験的空間。唯一、中央に配された棚だけが、何もない空間の中心を形成している(兵庫神戸1986年)YOHJI YAMAMOTO 神戸/撮影:Nacása & Partners Inc.
YOHJI YAMAMOTO 神戸/撮影:Nacása & Partners Inc.
日本的空間原理の本質は、日本の景観にも表れています。ヨーロッパが数学的・幾何学的に街づくりをしたのに対し、日本は、ある瞬間に何が見えるか。その瞬間、瞬間の美というものを大切にした、いわば回遊式庭園のような概念の街づくりをしていたのではないでしょうか。そこに、どのような秩序があったのかと考えると、ヨーロッパのような人工的秩序ではなく、自然の秩序をベースにしていたと思われるのです。
自然の秩序というものは、四季の移ろいをくり返しながら長い年月をかけて完成していくものです。ですから、建物をつくるときも、道をつくるときも、自然の植生などを頭に描きながら行なっていたのでしょう。
自然というものは最初は混沌としていても、自然界が種の構成を遷移させながら、やがて極相に至るかのように、長い年月の後に秩序ある美しさを生み出し、それらが「地」となって建物や街並みの色や形という「図」との関係を調和させるのです。では、そうした「自然の秩序」をベースとする日本特有の「地」の感覚はどうやって培われてきたのでしょうか。
「靴を脱ぐ、座る」という
座の暮らしが育んだ水平感覚
おそらく僕と同世代の人たちもそうだと思いますが、僕はこの世界に入った当初、日本文化から意図的に逃げるようにして、憧れていた欧米のデザインを追いかけていました。ところが外国のジャーナリストが僕の仕事を見ると、極めて日本的なデザインだと言うのです。畳も障子も何も使っていないのに、一体なぜ、僕の作品は日本的に見えるのか。
日本建築のエレメントであるとか、装飾的なボキャブラリーを使うことが日本的というのではなく、日本には固有の空間特性、つまり日本的な「図」と「地」の本質があるのです。日本特有の「地」の感覚として、第一に挙げられるのが「水平感覚」です。では、なぜ日本人は水平感覚が発達しているのか。実は、日本人の空間感覚に多くの影響を与えたのは、「座る文化」と「靴を脱ぐ文化」なのです。
よく、西洋的空間と日本的空間との違いは、「垂直的空間」と「水平的空間」の違いであるといわれます。例えばシェークスピアの舞台は「遠近感」を必要とします。そのために舞台空間には奥行きと高さが不可欠です。しかし歌舞伎などの日本の舞台空間は、遠近よりも一望できることが要求されます。そこでは「水平性」が重要となってくるわけです。日本のデザインの水平感覚は、「地」となる室内空間が徹底的に水平に構成されたことに由来しています。土間、板の間、畳の間という、水平な床の変化の流れが待ち受けているわけです。
そして、「水平感覚」を生んだ生活は、常に床に親しむという座る生活であり、座る生活が眺める視線を生み出したことになります。静かに座って庭の自然を眺める。この眺めるという視線は目の左右の移動です。目の左右の移動は水平的に見る眼差しです。室内におけるすべてのものが水平にデザインされたのは、そうした眺める眼差しによるものです。そして、その水平感覚を実際に支えていたのが木造建築です。
木造建築における直進性のある意匠がもたらす水平感覚。その中で、建築史家の伊藤延男氏*1は、主体となった木の種類が、我が国固有の直線的木材、檜や杉のように、木目のよく通った、割りやすく加工しやすいものであったことに関連があると述べています。このような直線性は、鉄の丁具が伝えられた弥生時代以来のものです。日本の文化を一般に「木の文化」だといいます。それに対して韓国の文化は「土の文化」です。韓国の主となる木材は松のように曲がった素材なので、建築の外観、意匠には適しません。そこで土によって全体を覆うことになるわけです。そう考えると、木材の性質がどれほど文化の意匠を決定するかということが、恐ろしいほど明快ではないでしょうか。
装飾性の少ない住宅建築において、檜・杉の直線性そのものを意匠にまで高めたのが日本のデザインだといえるでしょう。そしてそのデザインとは、どこまでも広がる水平感覚とともにあったのです。また、日本の住居の開口部は、高さよりも広がりが重視されています。床に座る暮らしでは、直接的に建築素材に肌が触れます。
日本のインテリアデザインが今日においても素材に対して非常に敏感なのは、そうした生活感覚によるものだろうと思えます。座ることによって生まれる空間への「眼差し」はインテリアデザインへの視線を下げ、その視点から生まれるデザインは常に「水平を強調」したものとなりました。そして「座る文化」が育む水平感覚は、室内にいながら、外部の自然の秩序を「地」として感じることにも繫がっていったのです。

日本人が知っている「空」というコンセプト
日本特有の「地」の感覚として次に挙げられるのが「空」という概念です。日本人は、近代になって壁の世界に暮らし始めました。かつては柱と屋根を基本構造とするがらんどうの建物に、御簾や蔀戸などを立てて仕切るというのが、本来の暮らし方でした。やがて建具が生まれ、空間の仕切りが少し意識的になりましたが、それでもがらんどうに変わりはありません。
壁がないのが日本建築の原点です。日本的空間原理の本質は、この「仕切り」に対する感覚にも表れています。日本人にとっての仕切りには「認識の仕切り」と「明示的な仕切り」の二つがあります。工業化された近代以降は、壁などの「明示的な仕切り」でなければならなくなっていますが、もともとの日本人の感覚では空間に「線を一本引いた」ものも立派な仕切りだったのです。
空間においても、自分の認識によって自在に「仕切り」をつくったり消したりしていたのです。舞台における黒衣の存在も同じ。日本人にとっては舞台の黒衣は「ないもの」として認識できますが、欧米人には「不思議な黒い衣裳を着た人」として「あるもの」に認識されるわけです。
このような「認識の仕切り」は日本特有の空間認識に派生しています。日本の住居では「玄関」、「上がり框」で靴を脱ぐ場とそうでない場とを明確に分離します。履物を脱ぐといった行為に精神的な意味を見出したのが、日本の「靴脱ぎ文化」でした。
家とは、自然から人間のための空間を切り取り、囲ったものであり、見えない世界の悪霊、怨霊、死などから守るものでした。そう考えると、日本の家は未知の世界から聖なる空間を囲ったものであるともいえるのではないでしょうか。聖と俗、コスモスとカオス、彼岸と此岸、この世とあの世など、空間を二つの世界に分離、未知の世界との結界を設けたものが家でした。
靴を脱ぐ暮らし故に、日本人は逆に自然の秩序が織りなす「外の世界」というものにも敏感になれたのでしょう。靴を脱いで足裏から直接伝わる温度や四季の移ろいを、日々感じながら生きてきたのです。外と内を明確に分けながらも、家の中にいても自然と繫がっている。このような感覚も玄関という「認識」と「明示的」の両方を併せもった仕切りを経て、自然とも〝地続き〟の空間にいるからこそもてるものなのです。
こうした日本独特の空間の豊かさの本質をさらに追究していくと「うつ(空)」の美学に行き当たります。空であるとか、虚、空虚、空っぽなど、日本文化にとって大変重要かつ核心的なコンセプトです。つまり、常に、空っぽから始まるということ。最初から完成されていないのです。空っぽだから、いろんなものが入る可能性をもっているということです。
「うつ」の派生語に「うつわ」があります。うつわは、その中に、もう既に何かが入っていると、次のものが入らないわけです。ですから、日本文化の本質的なものは一回「うつ」に戻すわけです。戻して次のスタートを始めていく。要は変化です。変化を自在につくりあげていけるのが日本の空間であるといえるのではないでしょうか。
日本の空間でとても重要なことは、「変化の相」といい、変化こそ永遠であるという考え方です。諸行無常、常に物は変化し、変化させないと、暮らしは成立しないということが一方であるのでしょう。また常に「空」であるということは、いつでも元に戻すことができ、何回でも新しいものが立ち上がっていけるということです。地鎮祭で神様をお呼びするときにも地面に四本の竹の柱を立て、注連を張ることで神域ができます。神様は神社にだけおられるわけではなく、常に「空」である真新しい場所にお迎えすることができるわけです。
近代が嫌った「ゆらぐもの」がもつ
精神の解放感と心の豊かさ
また、近代は「ゆらぎを生じるもの」、「ぼけたもの」、「柔らかいもの」、「不定形なもの」などを、不明瞭、不揃いであり、征服すべきもの、弱いものとして嫌いました。しかし、自然のつくり出すものは、すべてこうした特性をもっています。「故郷を失ったデザイン」という言い方がありますが、人間の故郷とは、自然であり、宇宙であり、また地域であり、民族です。日本のインテリアデザイン、日本固有の空間特性の故郷は、申し上げているように常にゆらぎながらも一定の秩序を感じさせる「自然の秩序」にあるはずなのですが、20世紀の工業化社会では、そうした〝ゆらぎ〟は計算できないものであるとして排除されていきました。
その結果、どのようなことが起こったのでしょうか。人間の営みの場である建物、空間デザインにおいても「工業化」が上位概念として提示され、人間の精神性もそこに合わせていくということが起こりました。
つまり、それまで自然の秩序を「地」としてきた日本のインテリア、空間特性が、工業化を「地」とするものに変容していったのです。工業化を上位概念に置いた近代では、自然の中にある「ゆらぎを生じるもの」、「ぼけたもの」、「柔らかいもの」、「不定形なもの」というのは征服すべきもの、弱いものという位置づけです。以前、ニューヨークの大学で講演をした時に、僕の話を聞いたアメリカ人の学生がこんな感想を伝えてくれました。
「日本人は弱さというものを多様な価値観で捉えている。そのことが非常に新鮮で驚きだった。アメリカ人にとって弱さとはネガティブなものでしかないのです」
その学生は、今日から弱さに対する考え方が変わるだろうと言っていました。そもそも「それだけのインパクトを与えるパラダイムを日本人が知っている」ということに、実は我われ日本人がもっと気づかなければならないのではないでしょうか。
強さだけを前面に押しだした社会認識、生活文化、産業構造、政治経済では、他ならぬ人間が窒息してしまい、同時に地球にも大きなダメージを与えてしまいます。
こうした状況において、デザインの役割とは何か。「弱さ」は、美の根源をなすものであり、そうした美は、人の心に深い影響を与えるはずです。人はけっして強いものではなく、弱さを抱えて生きています。寂しさ、わびしさ、はかなさ、心細さ……それらがあるからこそ、人は愛し、慈しむのです。
そうした心のありようを美に転換したのが日本の文化でした。一切のものは生滅、変化して常住ではない、常なるものは何一つないとする「無常観」が生まれたのは、中世。それを「無常美観」、わび、さび、幽玄の閑寂な美へと転換させたのが、日本文化です。ものはいつかは壊れるということを想定したものづくりが必要になるでしょう。デザインとは、常に人の心に向かって行なわれるものなのです。自然の織りなす「ゆらぎ」や「不揃いの中の調和」こそが人の故郷であり、人のための心地良い環境です。
「地」が自然に近いほど
「図」を際立たせることができる

日本人にとって、もっとも空間の豊かさを享受できるインテリアデザインとはどのようなものなのでしょうか。つまり「瞬間、瞬間」で移ろいゆく自然と共にある「変化と永遠」を感じられるのは、どのような「図」と「地」なのかということです。
それはやはり、自然の色をベースにしたニュートラルな「地」の空間に、日本の四季の色合いが映える状態ではないかと思います。「地」が自然に近いほど、「図」となる家具や装飾、光などを際立たせることができるのだということです。
現代の日本で、自然の色をベースにしたニュートラルな「地」の空間は何によってつくることができるかといえば「木の床」だと思います。
僕は独立した頃から、皆が避けていた「木」を使うことに全然抵抗感がありませんでした。当時、友人に頼まれてマンションの改装をよく手掛けました。その際、マンションに何が欠けているのかと思ったとき、自然素材だということに気がついたのです。高度経済成長時代のマンションの床はビニール系カーペット全盛期。もっと人間に近い、自然に近い素材を身近に感じるべきだと思い、マンションの床を全部フローリングにしました。
また、最近は素材の使い方も、巧みになってきました。あとはセンス、あるいはバランスの問題です。例えば、どのくらいの木地の面積に対して、どのくらいの白を配置するかというようなことです。固定したものには強い色はつけないことが肝要かもしれません。そうすると、絵を飾ってもきれいに見えますし、絵を取り替えても馴染みやすくなります。道具で色をつくり、空間で地をつくるというわけです。
このように考えると、日本人にとっての真に豊かな空間とは、やはり「自然の秩序」をベースとしたニュートラルな「地」のある空間なのではないかと思います。「地」が確かで揺るぎないからこそ、色や形という「図」が生きてくるのです。
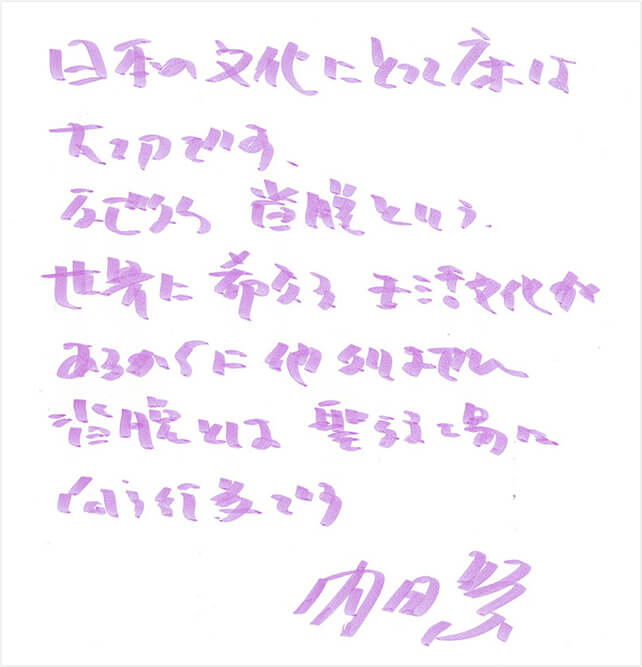
(*1) 伊藤延男(いとう・のぶお)…1925年生まれの建築史家。東京帝国大学建築学科大学院修了。工学博士。1947年国立博物館に入り、奈良国立文化財研究所建造物研究室室長、文化庁文化財保護部建造物課長、文化庁鑑査官、東京国立文化財研究所所長を歴任して退官。のち神戸芸術工科大学教授。著書『中世和様建築の研究』(彰国社)、『日本の建築』(社会思想研究会出版部)、『古建築の みかた』(第一法規出版)などがある。