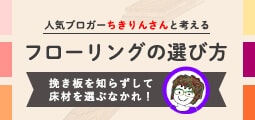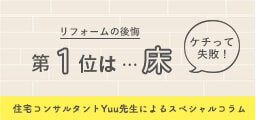名前をなくすことで機能が拡張される

「床」の本質とは何か―。
もともと僕が育った家というのが、いわゆる昔の町家でした。間口が狭く、やや薄暗い玄関を入ると、うなぎの寝床のように細長い空間が奥に続いている。お風呂は五右衛門風呂で、家の真ん中には中庭があり、雨の日には傘をさして台所に行くような……。
そんな家に生まれ育った僕は、いつも「自分だけの空間」を探していたのかもしれません。家の中で唯一、何もない空間だった「板の間」に自分の大事なものを集めて自分の部屋のようにしていたのを覚えています。
大人から見れば、ただの「板の間」。でも、子どもの僕にとっては、自分のものに囲まれて、寝転がることのできる、自分がつくりあげた贅沢な空間。板の間での昼寝って、ひんやりと冷たくて本当に気持ちがいいんです。しかも、細長い町家だから風通しもいい。僕にとっては、床の原体験ともいえるのが板の間の〝自分だけの部屋〟だったわけです。
大人になって社会に出ると、当たり前ですが「これは、この用途のため」というように、すべてのものや場所に名前がついています。そして、基本的にはその「名前」に従って生活や仕事をします。「廊下」と呼ばれていたら、それは廊下なんだなとしか思わない。そこに人は「廊下」以上のイメージも価値ももたないわけです。でも僕は、その「当たり前」に接するたびに、どこかで「そうじゃないんじゃないかな」という思いももっていました。
例えば「コップ」は液体を入れて飲むことに使う道具です。普通は、その名前の用途でしか存在していません。でも、その名前を取ってしまえば、花瓶やペン立てに使おうとか、金魚鉢にしてもいいかなとか、積み上げて飾ってしまおうというように、自由な発想が出てくる。与えられた名前、決められている名前をなくしてみると、モノや空間はとても自由な存在になります。だから僕は、あえていろんなものから名前を外して「これって何をするものだろう?」と向き合うことにしたんです。
床は「いつ」床になるのか
僕の育った家もそうでしたが、昔の家や生活は、今ほど〝機能的〟ではなかった。今みたいに「LDK」なんていうものはない。居間なのか寝室なのか、食事をする場所なのか作業場所なのかもわからない。名前で規定されていない分、まるで家そのものが「道具」であるかのように自分たちでうまく使いこなしていました。
今の時代は、家や家具、家電も最初から「これは、このためにあるものです」と、とても機能的に利便性の高い状態で僕たちに提供されています。もう、それ以上自分で工夫する必要もないから、手を入れるという感覚ももたなくなります。そのために「愛着」が薄れているようにも思うわけです。
「床」にしても、規定された床を考えるよりも「いつ床になるのか」ということのほうに興味があります。段差があって人が座れる場所があれば「床になる」のかもしれない。でも、それを世の中は「床なのか椅子なのか」と規定することで定着を図りたがる。床に本を積んで勉強したら、その場所は、床なのか。実は、人の行為がそれを決めているということです。
哲学者の野矢茂樹先生が書かれた『はじめて考えるときのように』という本があります。僕がとても影響を受けた本ですが、読み進めていくと、どんどんいろんなものの境界線について考えさせられるのです。
建築家が「オフィスをつくってください」と頼まれると、その瞬間に〝オフィス〟という名前が立ち上がって建築家を支配しようとします。日本のオフィスというと、蛍光灯に照らされた無機質な白い空間で、どの会社もとても無個性です。本来、他の会社と違ったものを生み出すための空間が、どこも同じというのはおかしいでしょう。
最初に「オフィス」という言葉を聞いたときに規定されるイメージではなく、どの瞬間にオフィスになるのかを考える。ものの価値が決まる瞬間というところに考えの軸を動かしていくと、すごくいろんなものが開けてくる気がしないでしょうか。
いろんなものを「はじまり」に戻すこと。それも建築家である僕たちの仕事なのだと思います。こうあるべきという、いろんなイメージや概念にとらわれて不自由になっているものから「逸脱」する手段として建築があるのかもしれません。
不真面目に考え真面目につくる
世の中の定義から逸脱することで、より多くの人に受け入れられるようになった。そんな逆説のようなプロジェクトが静岡県沼津市の「cafe/day」(2011年)です。
もともとは居酒屋だった物件をリノベーションしてオープンカフェにしたのですが、スケルトンにするのではなく、照明や床柱などには居酒屋の名残が残っています。けれども「居酒屋」という名前を一度取って考えると、キッチンやカウンターを塗り替え、テーブル、椅子などにカフェの構成要素があれば「カフェ」として成立するわけです。カフェの床をアスファルトをモチーフにして自動車学校の延長線のように、どこまでも道路が続く空間をイメージしたものに替えました。店内のサインも、まるで交通標識みたいにして。中を外に近づけてオープンカフェをつくるのではなく、外が中に近づいてくるほうがいいんじゃないか、という逆転の発想です。
ちょうど、ミニクーパーのシートをオークションで見つけたのですが、黄色いラインがデザインされていて「まさにこの店のためのシート!」と、思わず落札して、キャスターをつけたチェアに改造したりもしました。
神奈川県藤沢市につくった「まちの保育園キディ湘南C X(シークロス)」(2011年)の場合は「そもそも保育園の本当のクライアントは誰なんだろう」というところから考えました。
保育園のクライアントは子どもたちです。ですが、世の中の保育園といえば、何歳児の部屋というようなカテゴリの枠をつくり、文字通り一つの枠の部屋の中に閉じ込めてしまいます。決められた場所で決められたもので遊んでいなさいというように。それって、実は「愛のある虐待」じゃないかと思っていました。どこで何をして遊ぶかを自分たちで〝発見〟していくのが子どもたち。それなら、発見のきっかけがたくさんあるような保育園にしようと考えたのです。
「絵の部屋」、「本の部屋」、「水の部屋」、「料理の部屋」といった、たくさんの小さな部屋を子どもの大きさに合わせて設計し、大きな空間の中にばらばらに配置しました。子どもたちにとっては発見がたくさんある大きな街。街そのものが遊び場ですから、間仕切りも設けていません。床に線路を描いたり、建物の外側を黒板塗装にしたりすると、それだけで子どもたちは想像力を目一杯働かせて、自分たちの遊びをつくっていくのです。
僕の性格かもしれませんが、皆が「こうあるべきだ」と言うと、絶対に「本当にそうかな」と考えます。周りがみんな「当たり前のこと」をやろうとしているのなら、誰かがちょっとぐらい不真面目に考えないと新しいものなんて生まれてきません。そうして、不真面目に考えたことを真面目にやるというのが大切なのではないでしょうか。
人との関わりが床をつくる
自然素材として木を使うことも好きです。木は、いろんな意味で「育つ材料」だと思うからです。木に囲まれていることで育つもの、直接触れて育つもの。いろんな可能性が木にはあると思います。とはいえ、加工されたものでしか「木」を使うことを考えないというのも、どこかで考え方が固定されてしまっているかもしれません。
もっと自然な状態で「木」と関わる建築ができないか。極端に言えば、森をつくっているのか家をつくっているのかわからないような「木の家」というのもあっていいと思いませんか?今まで建物の中でしかやれないと思っていたことを、どんどん外に向けてやってみるのもいいでしょう。例えば、外で飲むビールはおいしい。昼寝だって爽やかな季節に外でするのは、とても気持ちがいい。それなら外に床が出来ることで、人間の活動がもっと広がるかもしれない。そういったことも建築のやれることですし、やらなければいけないことでしょう。

住宅なら、まず考えるのは「人との関わり」がどうあるかということ。なぜなら、人との関わりがあって、はじめて「床」が定義され、そこからいろんな建築が立ち上がっていくからです。そうやって「はじめて考えるときのように」床を考え、住宅を考えていけば、きっと「できたらいいな」の世界がもっと広がっていくと思います。
最初から公共性を起点にせず、自分がいいと思ったものに公共性をもたせる。最初から皆がいいと思うようなものは、「できたらいいな」を突破する説得力ももたない。
個人の言葉が価値をもつ時代だからこそ、建築もこれまでの当たり前をなくして突破する力をもっていたいと思います。