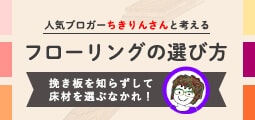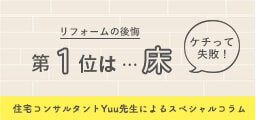新たな素材との出会い
「素材の建築家」― 。 私は、そのように称されることも多いのですが、なぜいろいろな素材を通して新たな建築領域に挑戦をしていったのか。その大きな理由の一つにコンクリートというものに対する抵抗がありました。どうにも好きになれない。にもかかわらず、大学で教わるのはコンクリートを中心とした建築です。
あらゆる建築がコンクリートというものを前提にして、どんな建築プランがいいかを問う。どうも、そのやり方自体が根本的に違うんじゃないか、その前提から建築を考え直してみてもいいのではないかと思ったのです。実際に自分で設計をやり始めると、なおさらコンクリートを前提とした建築が人間の快適さと相容れないものに感じられ、新たな素材の試みを積み重ねてきました。
その皮切りとなったのが、1994年に完成した四国の四万十川上流に位置する高知県梼原(ゆすはら)町の『雲の上のホテル』です。
これは、私の中で初めて「木」が目的になった建築でした。それまで違和感を覚えながらコンクリート建築をやってきたわけですが、このとき梼原町の町長さんから言われたのが「うるさい注文はしない代わりに、木を使うことだけはやってくれ」ということ。それも、地元の梼原の杉を使うのが絶対条件でした。
新しい素材に関わることができてうれしい反面、これは大変だなと思いました。なぜなら、木を使うということは設計においてもコンクリートとは全然違ったディテールが数多くあるのですから。その後2006年に完成した『梼原町総合庁舎』も手掛けましたが、木でつくるということは自分にとっても非常にいい緊張感をもたらしてくれた体験でした。
木の良さというのは、単にデザインが気持ちいい、見て気持ちいいというだけではありません。もっとパースペクティブ(物事の考え方)を俯瞰させ、地球全体にとってもプラスになるという技術的な側面も忘れてはならない。
木という素材には「寸法」があります。自然の制約から与えられる寸法というものがあり、それに基づき切り分けられているのが特徴です。自然の制約というものは、 窮屈なものではありません。むしろ、人間という小さな存在(スケール)に適した、 安心できる素材であることもコンクリートにはない良さではないかと思うのです。
すべての素材にヒエラルキーはない

村井正誠記念美術館 ©Daici Ano
すべての素材は等価であるというのも私の基本的な考え方です。
そういった意味で、木であっても無条件に無垢材にこだわる必要はない。そもそも、木という素材の本物と偽物の境界というのもありません。どこまで薄くしたら、あるいはコーティングしたら木ではなくなるということもなく、すべては人間との関係性で決まってくる相対的なものでしょう。その空間で人間に安らぎを与えてくれるものがあったら、薄くてもきちんと自然材料としての役割を果たしてくれていると思うわけです。
建築にはいろいろな条件が付いてまわるもの。資金が潤沢で、どのような木も自由に使えるスケールリッチもありえれば、資金は少ないけれども木のやすらぎを感じられるようにつくられた空間というのもあります。
そういった点で、建築というのは、いろんな条件を全部のみ込むようなおおらかさと強さが必要だろうと思います。
どうしても建築というものはコストの高いものから安いものまでを取り扱うときに、「高い素材は高級な生活に対応していて、そこが文化の中でもいちばん上質な部分だ」というようにヒエラルキーを決めてしまいがちです。
とりあえず大理石を使うと空間のグレードが高くなるから、建物をよく見せるために大理石を使ったり、逆に安い材料を仕上げに使うと、その空間にいる人間のレベルまで低いように見られたりするというヒエラルキー自体が貧しいのではないでしょうか。
どんな素材を使ってもコストの高い安いに関係なく、素材と人間がとても豊かな関係を結んでいくというデザインの仕方はあるわけです。それなのに素材のヒエラルキーみたいなもので自動的にデザインを規定するのなら、デザイナーや建築家は必要ないことになります。
むしろ、そうした既成概念や秩序を破壊して再構築することが本来やらなければならないこと。誰がつくったのかもわからない慣例や常識にとらわれてしまうことが建築のいちばんの敵ではないでしょうか。
不揃いの美学
樹種の木目や色目、照りなどの多彩な意匠力を最大限に生かし、樹種それぞれの個性を引き出して、その味わいを活性化させる。そのためには、天然木ならではの色みの変化を当然とし、節や傷ついた樹皮の刻印があることを自然の本質にするということ。
『村井正誠記念美術館*1』の設計にも共通項があると思います。私自身が、不揃いさによって物質のある本質が伝わってくるということに気づき始めたということもその背景にはあるでしょう。
人間の感じ方というのは不思議で、木のフローリングであれば、1つのピースを見ているだけではわからないものが、全体を見て、自然はこれだけのばらつきがあるんだということに気づき、そこで初めて伝わってくる材料の本質があるんですね。
ところが、これまでの建築の設計者というのは不揃いをはねるわけです。要するに不揃いであるということは欠陥だととらえる。そして不揃いを排除しているうちに、いつの間にか自然素材のいちばん大事なものが抜け落ちて失われていくことになります。
私は、その逆で、どうやったらわざわざ不揃いをつくることができるかというようなことを考えるのです。不揃いと繊細さというのは、対立するものではなく、逆に不揃いによってある種の繊細さが出てくるところがあり、日本の伝統の中にはどうもそういう技があるような気がしています。
例えば、木という自然の素材を使うとジョイント部分に僅かな隙間が生じます。では、その隙間が素材の価値を低くしてしまうものなのかというと、そうではありません。隙間があるからこそ、「木」というものの大事なエッセンスを感じることができます。素材そのもののもつ特性こそが魅力です。
わざと不揃いにすることによって、とても繊細な感じや優しさが出せる。不揃いのものがすごく荒っぽくて男らしいということでもありません。
日本文化というものは、それぐらい高等な技が存分に仕込まれているのです。このことにようやく日本人は気づけるくらいの成熟した時代がやってきたともいえます。20世紀というのは、そうした繊細な技を一度忘れてしまって、コンクリートに代表されるような海の向こうから来た技術を使いこなすだけで精いっぱいの時代だったのでしょう。21世紀が少し進んで、もう一度、日本人の美学が熟し始めているような気配があります。
特に新建材の業界では、今までは色みを揃えるという、それ一辺倒でやってきたといいます。カラーフロアーでも、色出しが2000色ぐらいになっていた。ちょっと違うだけでクレームになったり、あるいは床と建具をまったく同じ色にしなければならなかったりというところにすごいコストが掛かっていたんですね。「不揃いの美学」は、そのアンチテーゼとしての提案にもなるといえます。
裸足で触れる床の気持ちよさ

空間を構成する天井、壁、床、という要素のうち最も身体に密接に繫がっているのは床です。
なぜなら床は、重力がある限り人間は触れざるを得ません。人間は重力に逆らえません。自ずと、人間にとって床は外部とのインターフェースにあたり、人間が、自身で直接交渉できるのが床であるということになるわけです。
季節ごとに床から感じる温度の違いや、床の素材そのものがもつ硬さや感触といったものは人間の心理に大きな影響を与えています。そのことから、私の設計でももっとも床を重要視しているといっても言いすぎではないでしょう。
建築家は、平面図によって、建物が規定されると考えがちですが、私はそうではありません。床がどうあるかによって、その建築が決まると考えています。
また、私自身はデザインをするときに、壁というものを消し去りたいといつも考えています。床と天井の間に、人間をそっとおく。そうすることで人間本来の豊かさというものが体感できることを理想としています。
床には壁や天井にはない、身体との直接性があるために、動物としての人間は床に対してとても繊細です。
特に、日本人がその感覚をずっと研ぎ澄ましてきたのは、日本の住まいが吹き放しの空間を原点にもっているからということがいえるでしょう。壁で空間を区切るのではなく、たいていは建具で吹き放しです。そのために、日本人は床に対する注意が繊細であるということをイタリアの講演会でもお話ししたことがあります。
ただ、そのときは「イタリアにも床を大事にする文化がある。パケットフロアの床の感触を大事にして、わざわざ夏は裸足になって木の冷たい感じを味わう文化があります」ということを聞かされましたが、ともかく人間にはそういった床と身体性の関係を楽しむという文化があるように思えるのです。その延長線上には、靴を脱いで裸足で過ごすという日本の文化が世界にもっと広がっていくということも十分あっていいでしょう。それこそ、食文化である寿司が広がっているのと同じぐらいに。
衛生的に見ても、裸足の生活は、外の土ぼこりを家の中に持ち込むよりもいいわけです。環境的な生活技術として、裸足を見直してもいいぐらいかもしれません。1995年の「ヴェネチア・ビエンナーレ」でもそういった提案をしました。そこでは「大統領を裸足で歩かせるのか」と、かなり怒られたりもしたわけですが、やはりそれから随分、考え方も環境も変わってきているように思えます。
2007年のミラノサローネの『つなぐ TSUNAGU』では、靴を脱いで過ごす空間でみんなが本当に気持ちよさそうに裸足で歩いて、なかなかその空間から立ち去りませんでした。普通、ミラノサローネでは、見るものがたくさんあるので、皆早足で見て回るわけです。けれども、あの空間はものすごく滞留時間が長かったのが印象的でした。
このときのコンセプトモデル「TSUNAGU」というのは、単に境界を曖昧にした透明性という物質的な理念ではなく、それを超えた何かがあるということを示したかったわけです。
私自身、今でも京都の寺で、縁側を素足で歩くのが大好きです。足の裏が床に触れ、気持ちよく、その感触に癒されるようです。その時間の豊饒さというものは、日常と非日常、無常と常住などあらゆるものの境界を越えて、私に語り掛けてくれるものをもっているように思えてなりません。
20世紀の最初というのは、近代建築という流行の中で、透明性とはガラスのことでした。それに対して21世紀の今、繫ぐと言ったときには、単に透明なだけではなく、その向こう側とこちら側の関係の親密性のようなものも表しています。
「TSUNAGU」のようにガラス越しではなく、むしろ格子をつけたほうが、よりこちら側と向こう側の深い関係性というものを感じさせることができるということ。
そういうデザインを発信していったならば、20世紀の透明性というのを超える何かができるかもしれません。それこそが日本が世界に発信できる美学なのではないでしょうか。
*1 村井正誠記念美術館
1999年、日本の抽象絵画を拓いた村井正誠は93歳でその生涯を終えた。アトリエを保存して、新しいエンベロープ(膜状の構造)で囲むデザインで、その新しい外装を構成する部材として古い建物の外壁材を再利用しているのが特徴。不揃いの美学を体現している(所在地:東京都世田谷区中町、2004年竣工)